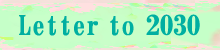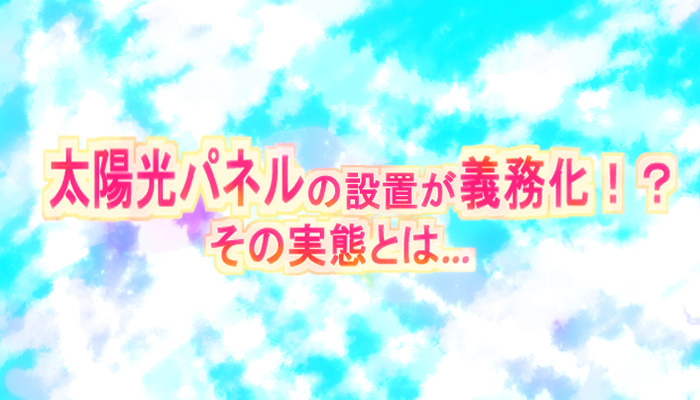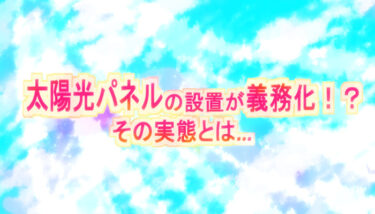2022年初頭に驚くべきニュースがありました。
それは小池都知事が脱炭素に向けて本気だという事が伝わるものでした。
その内容は東京都の新築住宅に太陽光発電のパネルの設置を義務付けるというものです。
もちろん、その太陽光発電パネルの導入について、都として補助金もつけ2022年度予算に組み込むというものです。
春を目途に検討されている現在の都の検討案では設置義務を負うのは家主ではなく大手住宅メーカーだということです。
そしてその計画では都内の年間新築数の5割にあたる2万戸に太陽光パネルが設置されることになります。
いかにメンテナンスを進めるかなどの問題がありますが、これが実現すれば脱炭素に向けて東京は大きな一歩を踏み出すことになります。
このように東京の脱炭素化に向けて明るいニュースがある一方で、日本の再生可能エネルギーの値段は、世界の平均より二倍以上高いという残念なニュースもあります。
2020年度、世界では太陽光、風力が石炭火力発電より安く発電できるようになりました。しかし日本では必要な機器や工事のコストが高いので、まだ再生可能エネルギーのコストが高いままです。
そして再生可能エネルギーの導入量も2019年実績では世界一のドイツの42%にくらべ、日本は18%にとどまっています。
その世界一の再生エネルギー王国ドイツでは電力システムそのものを変える巨大な発電ネットワークシステムが始まっています。
それは一言でいえば電力をデジタル管理する仮想発電所システムです。
ご存じのように太陽光発電などの再生可能エネルギー発電は天候に大きく左右されます。その欠点を補うためにドイツ全土の太陽光発電設備や蓄電池を備えた住宅や工場などをネットワークで接続します。そして発電量が多い時に地域の蓄電池に分散して貯蔵し、足りなくなった時にそこから供給したり、家庭からの発電で補います。
仮想発電所を運営する『ネクスト クラフト ヴェルケ』のヨッヘン・シュヴィルCEOによれば「皆がエネルギーの消費者であり、生産者でもあります。エネルギー転換とはエネルギーの民主化なのです。我々はEU全体を束ねる仮想発電所として再生可能エネルギーをひとつにまとめ国境のない電力システムを実現したいと考えています。」とこのように巨大仮想発電所システムの事を語っています。
これだけのみならずEU全体ではCO2排出の75%をエネルギーが占めることから種々の政策が推し進められています。
それは2025年までに100万基のEV充電スタンドを整備することや2030年までに住宅、公共施設などの建物の大規模な断熱化をすすめることなどです。このような国をあげての脱炭素への大きな転換は残念ながら日本ではまだなされていません。
そのような状況の中LCCM住宅というCO2収支をマイナスにする住宅がミサワホームから発売されました。
LCCMとは(ライフ サイクル カーボン マイナス)という意味で建築時や廃棄時に出す全てのCO2を勘案しても、長期的に見てCO2収支をマイナスにする住宅のことです。
太陽光パネルを沢山設置しながらも一見普通の住宅のように見えるのは、瓦屋根と一体型の太陽光パネルを使っているからだということです。通常の倍の量の太陽光パネルの設置が可能だということです。
そして、余ったエネルギーを他の住宅で使って貰うという工夫でエリア全体でCO2削減が見込めるそうです。
またそれだけでなく、断熱効果の高いサッシを使うことで消費エネルギーを減らしたり設計時に多様な使い方が出来る設計にして改修工事でのCO2削減をめざしているそうです。
ミサワホームの説明では建築後28年で建物の一生(建築時や廃棄時も含め)にかかる全てのCO2をマイナス収支にもっていけるそうです。
ただし建築費用は110平方メートルの住宅で通常より約250万円高くなります。
現在の補助金の上限は125万円だということなので、こういう所にこそ国は東京都を見習って補助金を大きくつけて脱炭素化をすすめてほしいと思います。
このように脱炭素化が個人や企業の個々の努力に委ねられているのが日本の現状です。
このままでは日本は世界の脱炭素化の潮流から取り残されてしまいます。
COP26での日本の宣言を現実のものにするにも国は今年度中に脱炭素化へ大きく舵をきる事が必要だと思います。