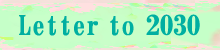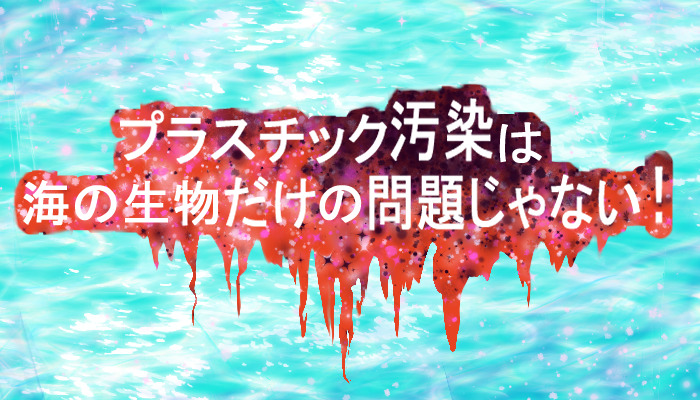プラスチック汚染というと私達は海亀やクジラの体内に取り込まれたプラスチックのレジ袋などを思い浮かべます。そのニュースに映る海洋生物の痛々しい姿に心痛める人も多いと思います。しかし残念ながら、プラスチック汚染の問題は海洋生物に留まるものではないのです。
現在かなりの数の研究者から
「食物連鎖の頂点にいる人間に巡り巡って、プラスチック汚染の害は及んでくる」
と指摘されています。
ところで今は私達の生活に無くてはならない物になったプラスチックはそもそもいつごろから使われるようになったのでしょうか?
それは1950年代からで、当時「20世紀の夢の発明」と呼ばれていました。便利で丈夫、そして安価ということから当初200万トンの使用から現代までに83億トンの使用と、その使用量はものすごい勢いで増加しています。
特に日本では欧米諸国にくらべ、必要以上に衛生を求める風潮があり過剰な個包装やカサ増しのための包装の大型化などの問題があります。
最近ではシャウエッセンを販売する日本ハムがパッケージの小型化を業界全体で取り組むという動きがありましたが、まだまだこの問題の解決には至っていないのが現状です。
そして日本では1995年に容器包装リサイクル法を制定してプラスチックごみの84%がリサイクルされていると発表されていますが、その4分の3が”焼却処分”されているのが実態です。
この”焼却”は日本のリサイクル法では”熱回収リサイクル”としてリサイクルの1つとして認められていますが、国際的には認められていないやり方です。
なぜならリサイクルとは本来の言葉通りに”リ・サイクル”で「もう一度サイクルに戻すこと」つまり「再生利用」することだからです。プラスチックごみを燃やして多量のCO2を出し温暖化につながる日本の”熱回収リサイクル”は本来のリサイクルからはほど遠いものです。
世界の現状はというと現在使用されているプラスチックのうち容器包材は36%、建築資材は16%、そして繊維は14%です。
そのうちリサイクルされているのはたったの9%で燃やされているのは12%になります。残りの8割は埋め立てなどのゴミの状態で地球に積みあがっていっているのです。そしてこの積みあがったプラスチックごみの一部が川から海へ流れ出し、海洋プラスチックごみになってしまうのです。
流れ出した海洋プラスチックごみは世界の年間消費量の1割、3000万トンにもなります。
そして海洋プラスチックごみの誤飲により、海洋生物の命が脅かされていると科学者は警鐘を鳴らしますが話はそこに留まりません。
プラスチックごみを胃にため込んだ海鳥が繁殖力を弱めてしまったり、魚、貝類の成長にマイクロプラスチックが悪影響を及ぼし、本来育つはずの魚の量が減ってしまい”生態系そのものが縮小し始めている”といった恐ろしい研究結果も出ているのです。
最近よく耳にする、マイクロプラスチックとは波や紫外線などの影響でプラスチックが5mm以下に砕けたもので、前述のように生態系への影響が懸念されています。
もちろん人間もその例外ではなく、マイクロプラスチックそのものだけでなくそれに含まれる添加剤という化学物質の影響が心配されてもいるのです。
添加剤とは紫外線吸収剤、難燃材、酸化防止剤など人体に取り込まれると有害となるものです。
東京農工大学の高田教授によれば「プラスチックは運び屋、トロイの木馬とも言います。プラスチックが生物の体の中に入ってそこから有害な化学物質が溶け出してくることで、その生物を体の中から攻撃してしまう」「長期的には毒が染み出してきて、回りまわって人に入ってくる。影響が数十年、あるいは世代を超えて出るところが怖いところだと思う」などと人体への影響を危惧しています。
また有害な化学物質を取り込むことで、甲状腺ホルモンの異常を引き起こし、脳に悪影響を及ぼし、自閉症やADHDなどの症状を引き起こすのではないかとも言われはじめています。
その上マイクロプラスチックは海洋だけでなく、大気中にも漂いはじめているという研究結果も出ています。この場合プラスチックは細菌レベルまで砕けた”ナノプラスチック”という微細な状態になり、人体に侵入し健康を脅かす新たなリスクとなっています。
つまりプラスチックごみはマイクロプラスチックやナノプラスチックという微細な状態に変化し、人体に有害な化学物質や微生物の運び屋となってしまうのです。
「生態系に迷惑をかけないプラスチックの管理の仕方を人間は考えていく必要があると思っています」これは京都大学の田中准教授が語った重い言葉です。
さて、私達はどのように行動したらよいのでしょうか?
その大きな指針の1つとなるものに「循環型経済」というヨーロッパなどで主流になりつつある考え方があります。
次回はその「循環型経済」と「プラスチックリサイクルの現状」について書きますので、興味を持たれた方はぜひ次回の記事も読んでみてください。