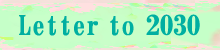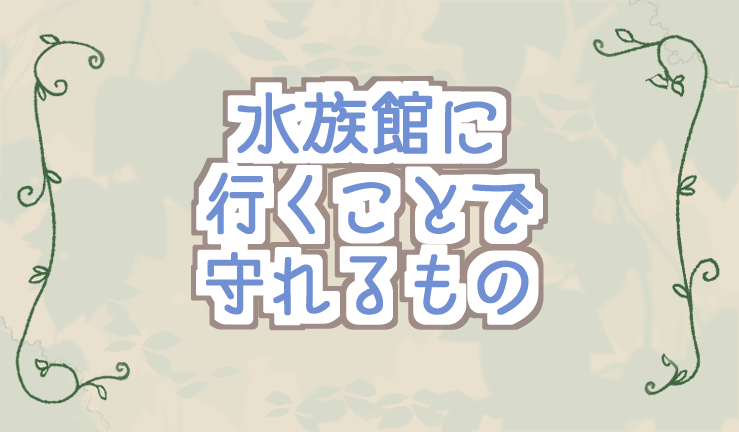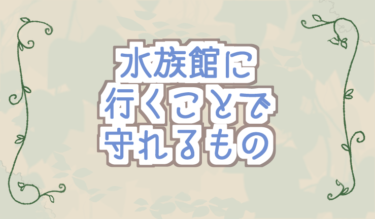今回は生物多様性を守るために水族館が行っている活動について書いていきたいと思います。
私の住んでいる都内の水族館の取り組みについて、まず都立の葛西臨海水族館の取り組みです。
かつては身近な生き物であったアカハライモリの保全活動をしています。
2002年から多摩地域の生息地で繁殖に必要な水辺環境を整えたり、モニタリング調査を行っています。
その結果、繁殖とともに個体数の増加がみられるのです。
また、飼育することで、同じ地域個体群を維持し、繁殖させる体性をとっています。
またトビハゼを開園当初から展示しており、日本初の水槽内での自然産卵による繫殖に成功しています。
トビハゼはかつて、東京湾の広大な干潟に多く生息していたようです。埋め立てや、河川改修、護岸整備、水質汚染などにより生息数が減少し、現在では準絶滅危惧種になってしまっています。
そしてミナミメダカの調査も2006年からおこなっています。
メダカには同じ種でも地域ごとに遺伝的な違いがあり、その多様性を守る必要があります。そして、安易な放流はその大事な多様性を損なう可能性があることを学校などで伝える活動もしています。
日本に生息するメダカは2012年に発表された論文によると「ミナミメダカ」と「キタノメダカ」の2種類に分けられ、東京を含む南日本に生息するメダカは「ミナミメダカ」です。そして、その中でも東京生まれ、東京育ちの家系で他の場所のメダカの血が混じっていないメダカを葛西臨海水族館は「東京めだか」と名付け、その保全に取り組んでいます。
また小笠原陸産貝類の保全にも取り組んでいます。
そのうち「カタマイマイ」「アナカタマイマイ」の2種を環境省からの協力要請を受け、2017年9月から飼育、繁殖を開始しました。
2011年6月に世界自然遺産に小笠原諸島は登録されましたが、その登録理由のひとつが100種類にも及ぶ陸産貝類の進化の多様性でした。
しかしながら、外来種のプラナリアやナズミなどによる捕食などが原因で陸産貝類の多くが絶滅の危機にあります。ここでも生物多様性を守るために水族館は頑張っています。
ここから私営の水族館のうち、すみだ水族館とサンシャイン水族館の活動を紹介します。
東京スカイツリータウンにある、すみだ水族館では絶滅危惧種の生き物たちの今を伝え、各種機関と協力しながら種を絶やさないための保全活動をしています。
その中で特筆すべきは「アオウミガメ」の保全活動です。
2012年の開業時より小笠原村と協力して絶滅危惧種の「アオウミガメ」の赤ちゃんを1年間預かり、大切に育てたあとに生まれ故郷の海に還すというものです。コロナ禍の中でもスタッフ総出で地道な活動を続けています。
池袋のサンシャイン水族館では”サンゴプロジェクト”を行っています。それは2006年から続けられているもので沖縄県恩納村の協力のもとサンゴ礁を再生させるものです。
そのために殖やしたサンゴを海に還す「サンゴ返還プロジェクト」と沖縄の海でサンゴを育て、産卵させることによりサンゴを殖やす「サンゴ礁再生プロジェクト」の2本立ての活動をしています。
ところで生物多様性を守るために、なぜサンゴを守ることが必要なのでしょうか?
それはサンゴ礁が海の生物多様性を育む”いのちのゆりかご”のようなものだからです。
そして山の木が根を張ることで、山の環境を守るようにサンゴ礁は海底を支えています。
そのことで海流に大きな変化があった時もサンゴ礁の海は守られます。このようにサンゴ礁は海を穏やかに守り、そこに棲む生き物たちも守っています。
そのためサンゴが死んでしまうとサンゴ礁に棲んでいた沢山の生き物達が棲み家や産卵場所を失ってしまいます。その結果、生態系が崩れ、やがては生き物のいない海になってしまいます。
今、温暖化による海水温の上昇によりサンゴの死である白化現象が起きています。そしてオニヒトデの食害や土砂の流入などでもサンゴ礁は減少しています。
しかし、この「サンゴプロジェクト」には嬉しい報告もあります。目視による魚種のカウントで2020年には25種だった魚種が、2021年には倍近くの40種になったそうです。確実に成果が出ているようでこの先が楽しみですね。
このような私営の水族館が、1館、1館出来る限り生物多様性を守るために頑張っている姿を見ると、そこに携わる人達の生き物への深い愛を感じます。
都営の葛西臨海水族館は東京動物園協会としてネットワークを持ち、他の園と相互に情報共有できる恵まれた立場にあります。
そのようなネットワークを都営、私営の垣根を越えて水族館同士が作れていけたら、海の生き物の生物多様性を守るために大きな助けになるのではと、個人的には思います。
ぜひ皆さんも水族館の頑張る姿を、水族館に行くことで見守ってください!