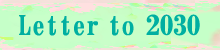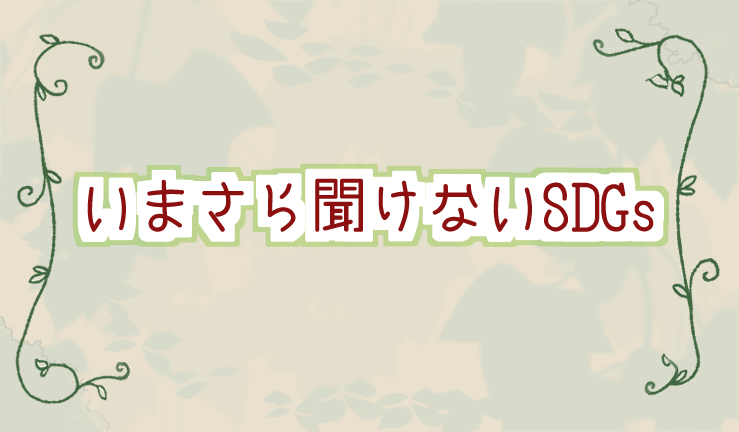SDGsという言葉を最近よく耳にします。
「この考え方はSDGsだ。」とか「SDGsの観点から見てBの商品ではなくAの商品を買うべきだ」などです。
SDGsが国連の定めた「持続可能な開発目標」の頭文字をとったものだという事はよく知られています。
しかし、学校でSDGsについて習っている子供たちほど私たち大人はSDGsの内容をちゃんと分かっていないように思えます。
そこで簡単にSDGsの説明をします。
これさえわかれば、子供に質問されてもSDGsについてちゃんと答えられます。
まずSDGsとは「Sustainable Development Goals(サステナブル ディベロップメント ゴールズ)」という英語の頭文字をとったものです。
Sustainableは「持続可能な」という意味で、Developmentは「開発」という言葉。Goalsは「目標」という意味です。
ではGoalsとは具体的に何を表しているのか、それは17の目標です。
そして、それは169のターゲットに分けられています。
キーワードは「17の目標」「169のターゲット」です。
ターゲットとは「いつまでに、何を、だれが、どのように取り組むのか」というように「17の目標」を具体的に落とし込んだものです。
ちなみにSDGsが採択されたのは「国連持続可能な開発サミット」においてです。それは2015年9月、ニューヨークの国連本部でのことで、2030年までに達成することが約束されました。
そして、日本政府といえば「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」を2015年に設置しています。案外、早い対応ですね。
SDGsで使われている「持続可能な」つまりサステナブルという言葉も最近よく耳にします。
もともと環境問題を解決するための考え方がサステナブルでした。平たく言えば
「孫子の代まで地球で今のように豊かに暮らしていくためにはどうしたらいいのか」というような考え方です。
地球上の資源は有限です。それを長く大切に使うためにはどうしたらいいのかを考えなくてはなりません。
短絡的に考えれば、資源をなるべく使わないで豊かな生活をあきらめて環境問題を解決するということになります。
しかし、私たち豊かな生活に慣れた先進国の人間はその生活を手放せません。そして、それ以上に今から先進国の人間のような豊かな生活を手に入れたい途上国の人々は納得できません。
そこで、色々な考えをすり合わせて新たに人々の意識に上るようになったのが
「生活を豊かにしながらも資源の消費を減らすことができるのではないか、そうして環境問題を解決しよう」という考え方です。
そのためには科学技術の革新(イノベーション)が必要です。そして、人々の考え方や社会の仕組みを変えることも必要です。
そのための道筋をしっかりと描いたのがSDGsなのです!
「17の目標」を設定し、それを「169のターゲット」に細分化し、世界上の様々な問題を解決するための道筋を描いたのがSDGsなのです。
国連本部で採択された決議案などと聞いても、遠い出来事のように思えることも多いのは事実です。
しかし、このSDGsは私たちの生活、そして、より良い未来にとても密接に関連しています。
今日からあなたもSDGsの考えを頭の隅に置いて生活してみてください。きっと何かが変わっていくと思います。